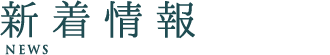このコラムでは「多摩」という地域に限定して、その中で現存する洋風建築を紹介してきたが、多摩の地域柄、名実共に建築家によって設計された様式建築はほとんどなく、大工棟梁が洋風建築を研究し、見よう見まねで建てた建物が大半であった。従って、施工者の洋風へのあこがれと模倣が相まって「和」ではないオリジナリティー溢れる力作が生み出されていた。そのような中で今回紹介する一橋大学は、東京帝国大学出の建築家・伊東忠太によって昭和初期に設計された建築である。「洋風」ではなく、西欧にルーツを辿る事のできる正当な「西洋様式」による建築なのである。
このコラムでは「多摩」という地域に限定して、その中で現存する洋風建築を紹介してきたが、多摩の地域柄、名実共に建築家によって設計された様式建築はほとんどなく、大工棟梁が洋風建築を研究し、見よう見まねで建てた建物が大半であった。従って、施工者の洋風へのあこがれと模倣が相まって「和」ではないオリジナリティー溢れる力作が生み出されていた。そのような中で今回紹介する一橋大学は、東京帝国大学出の建築家・伊東忠太によって昭和初期に設計された建築である。「洋風」ではなく、西欧にルーツを辿る事のできる正当な「西洋様式」による建築なのである。
伊東忠太は建築家・辰野金吾(東京駅を設計したことで有名)の基で建築を学び、その後東大の教授まで勤めた人物で、アカデミズムの中に日本建築の歴史を初めて位置づけした、日本建築史の生みの親としても知られている。建築史家にして建築家という類い希な能力の持ち主ということもあり、彼の残した業績は非常に独特で、正統な「様式」建築の延長上に、独自の世界を構築しているのだ。
伊東忠太に関するエピソードの一つとして有名なのが「エンタシス伝説」である。エンタシスとは柱の形状を表す建築用語で、一般的な柱が基礎から梁までまっすぐに立っているのに対し、柱の中間が曲線状にふくらみを持つ形のこを言う。エンタシスはギリシャ神殿の柱でよく見られる形状である。一方、日本に現存する最古の木造建築である法隆寺の中門の柱にも似た、ふくらみがあり、このような形を胴張りと言う。伊東はこの胴張りとエンタシスが似ていることに着目し、ギリシャの形がインド、中国を経て日本に伝わったという持論を立て「法隆寺建築論」として発表したのだ。さらに、伊東は持論を証明するために、日本からギリシャまで陸路の調査旅行に出かけるが、万人の納得し得るような決定的な証拠は得ることができなかった。とは言え、この論を否定できる証拠もないので、「法隆寺建築論」は今でも「伝説」として語られているのだ。僕も修学旅行で法隆寺を訪れたときに、バスガイドさんからギリシャと法隆寺が繫がっていると教わり、子供心にもロマン溢れる話であったことを覚えている。
建築家としての伊東忠太も特異な存在で、他に類を見ない意匠をデザインした。伊東の建築を身近に感じてもらうためには、作品を見てもらうことに尽きる。築地本願寺や湯島聖堂も伊東の設計だと言えば、行ったことのある人は納得できるのではないだろうか。キイワードは「怪獣」である。

一橋大学は建築様式としてはロマネスク建築と言われ、11世紀から12世紀の様式で建てられている。ロマネスクの特徴は、太い柱、半円アーチ、動植物を用いた多様な彫刻装飾が挙げられる。繊細というよりも、マッシブで安定感がある。ロマネスクが発展して13世紀から14世紀にゴシック様式の時代になる。ゴシックは中央の尖ったアーチで知られ、ロマネスクよりも垂直性が強調された洗練された様式である。東京大学、早稲田大学、慶応大学など多くの大学がゴシックで建てられたこともあり、大学と言えばゴシックのイメージが浮かぶほどだが、何故一橋大学ではロマネスクが採用されたのか……。藤森照信(工学院大学教授、東京大学名誉教授)が兼松講堂での講演会「怪物の棲む講堂」(平成15年)でこの謎を判りやすく説明している。内容を要約すると、大学の起源とされる中世ヨーロッパの修道院がロマネスク建築で建てられていたこと。そして、ロマネスク建築には「怪獣」が潜んでいたことも大きな要因の一つとしている。

キリスト教が今日のようにヨローッパに普及する前は、ゲルマン民族の土着的なアニミズムがあり、動植物も信仰の対象となっていた。その後、キリスト教が広まり、教会や修道院が建てられるようにった。建物の形としては初期キリスト建築のローマ風に習う一方、細部の装飾はアニミズムに由来する怪獣や空想動物の図像が組み込まれ、これがロマネスク建築となった。ところがゴシックの時代になると、これらのアニミズム的な図像はキリスト教的な合理性の中で無くなってしまう。様式建築の中に怪獣を同居させるためにはロマネスクで建てる必要があったのだ。
日本では山や水、火など自然信仰に由来する図像が建築に取り入れられることは珍しいことではない。神社仏閣に限らず住宅においても空想動物が建物に存在していた。現在でも和風建築の鬼瓦にこれらの図像を見ることができる。本鬼面の鬼瓦は阿吽の対で作られており、始まりと終わり、攻めと守りを意味すると言われている。実は一橋大学に取り付けられた怪獣をよく観察すると、阿吽の対となっている彫刻が多い。特に兼松講堂の中では、通路を装飾するアーチの端部毎に阿吽の怪獣がおり、これは仏教的なモーチフと言える。様式建築の中で洋の東西が融合されているのだ。
ヨーロッパでは宗教的な合理化の中で13世紀頃から怪獣を排除したが、万の神と共に生きる日本では1960年頃まで怪獣や空想動物と一緒に生きてきた。その後、生活の合理化や経済至上主義の中で、それらを置き去りにしてしまった。怪獣と共棲することは四季の恵みを与える自然と、災害をも持たらす自然の両方を受け入れる、日本的な自然観の中で生きることであった。このような自然観を崩してしまった今、数値では割り切れない様々な歪みに直面しつつある。伊東忠太の残した怪獣達は、忘れてしまった大切な何かを暗示しているのではないだろうか。
【参考文献】
■伊東忠太動物園 藤森照信他 筑摩書房 1995年
■日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか 内山節 講談社現代新書 2007年